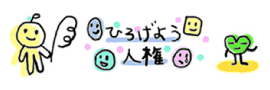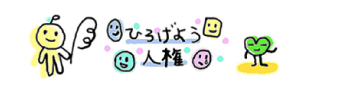資料館探訪 ウトロ平和祈念館

▲ウトロ平和祈念館外観
当館は、京都府宇治市にあるウトロ地区という在日コリアン集住地区の歴史を伝えてゆくために2022年に開館しました。戦争を背景に生まれたウトロ地区には、戦後もさまざまな差別や排除の中で、それを乗り越え新しい未来を紡いだ歴史があります。差別された可哀そうな人々の歴史ではなく、大変な困難の中でも自身の生活、人間としての尊厳を市民の力で守り抜いた実践を、私たちが暮らしているこの社会におけるさまざまな人権課題と向き合うためのメッセージとして伝えたいという思いから開館に至りました。
当館は3階建ての建物で、2階と3階が展示室となっています。2階はウトロ地区の歴史を扱う常設展示室で、人々の写真を多く展示し、その姿や表情を通じて、生きた人間の歴史を感じてほしいというコンセプトとなっています。また、在日コリアンを取り巻く当時の歴史背景や、社会構造を踏まえて展示し、その時代を生きた人々のリアルな群像を表現することに注力しました。3階の企画展示室では、広く人権と平和をテーマにした展示を行っています。

▲常設展示室
そして1階は来館者がくつろげる多目的ホールとなっており、住民やスタッフ、来館者同士の出会いの場として設計されました。屋外にはマダン(広場)を設置しました。これは「焼肉ができる広場が欲しい」との住民たちの声によるものです。ウトロ地区が、社会の分断がもたらすさまざまな困難を、出会いと連帯の力で乗り越えてきた経験があるからこそ、これからもこの場で出会いと交流を紡いでいきたいという思いがこのマダンに込められています。
ウトロ平和祈念館のキャッチコピーは、「ウトロに生きる、ウトロで出会う」。ウトロの歴史には、生きづらい社会の中でも一生懸命生きた人々の姿があり、それを可能にしたのは人々の出会いであったということです。これをさまざまな人権課題を乗り越えるメッセージとして、強く訴えたいというのが当館の思いです。
ウトロ地区は、戦争と植民地支配を背景に形成され、戦後もその連続性の中で、厳しい生活を余儀なくされました。同地区は戦争中、京都飛行場という軍事施設建設のために集められた、朝鮮人労働者たちの宿舎がその始まりです。戦後も故郷に帰れずこの地に定着し、在日朝鮮人集落を形成しましたが、周辺の人々からは治安が悪い等の偏見があり、また長らくインフラが整備されず深刻な衛生環境の中で厳しい生活を送っていました。

▲1961年当時のウトロ地区の全景
加えて1980年代後半のバブル期には、住民の知らないところで同地区の土地が転売され、約80世帯380名の住民が立ち退きを求められる事態が起こりました。戦争を背景に形成された経緯や、戦後も人々が生活をしてきた事実などは一切考慮されず、土地の所有権争いへと縮約された裁判では、厳しい状況の中でも築いてきた生活はすべて否定され、住民たちは土地を明け渡せとの命令を受けてしまいました。
しかしウトロの人々は、司法にまで否定された「あたり前の権利」を求め、敗訴後もあきらめずに声をあげました。希望が持てない、極めて厳しい状況であったにも関わらず、声をあげ続けられたのには、あきらめさせなかった地元を中心とした市民の存在がありました。
ウトロへの力強い支援は、1980年代中盤から始まりました。当時、上水道すら通っていない地区の状況を知った地域市民が、これは深刻な人権問題であると、水道敷設のための住民支援運動を展開しました。支援した日本の市民は「ウトロ地区-井戸水生活、全市民の恥」であると訴え、差別されている人々に問題があるのではなく、差別されている人々を取り巻くこの社会に問題があるとの考えから、「可哀そうな他者」ではなく、この社会を構成する一人ひとり、自分自身の課題であると、自分事として取り組みました。
このような姿が、ウトロの人々にとって大きな力、心の支えとなり、いつ強制執行が行われてもおかしくない状況でも、希望を失わず自分たちの街を守るための行動を続けることができました。
この立ち退き問題では、住民たちと支援者の訴えにより、韓国でも大々的な支援運動が展開されました。韓国の人々も、今の韓国社会の繁栄は切り捨てられた歴史の被害者の犠牲の上にあるとの認識から、今まで無自覚で何もしてこなかった韓国社会の責任を果たすべきだと、自分自身の問題としてとらえ、ウトロ支援のための市民募金を展開しました。
この募金に韓国市民15万人が協力し、ついには土地買取の支援金を拠出する予算案が韓国国会で承認され、日韓市民、在日コリアンらの市民募金と合わせ、同地区の3分の1を買い取り、その土地の上に日本の行政が立ち退きの対象となった人々を受け入れる公営住宅を建設することにより、この街のコミュニティを存続させる新しい街づくりが行われました。

▲2015年のウトロ地区の外観
ウトロ地区の歴史は、差別という不条理の前でもあたり前の権利をあきらめなかった人々と、これを自分の問題ととらえた日韓市民が、連帯して両国政府と行政を動かし、新しい未来を作り上げた実践の歴史です。その歴史を記録する当館は、見学をされた方々が心を痛め、落ち込むだけの施設ではなく、この人々の取り組みから私たちが今生きているこの社会におけるさまざまな課題を乗り越える、乗り越えてゆけるという希望と未来を感じてほしいと切に願っております。
出会いと連帯の力で課題を乗り越えた歴史を伝え、これからもこの街で多くの人々と出会い、つながって行く大事な拠点として、当館は多くの市民に支えられ運営されています。団体見学や出張講演のご依頼などお待ちしております。

2025.5 掲載