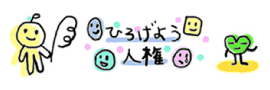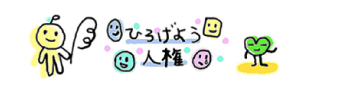災害で広がる格差に注目を
~気候変動時代に企業は何ができるのか

プロフィール
BuzzFeed Japan株式会社
ハフポスト日本版 編集長
泉谷 由梨子 (いずたに ゆりこ)
2005年に慶應大学総合政策学部を卒業後、同年4月から毎日新聞社記者。その後シンガポールでのNGO勤務などで広報職員の仕事も経験し、2016年4月からハフポスト日本版で勤務。2021年6月より現職。SDGs、女性・若者のライフスタイルやジェンダーギャップの問題、個人の働きかたと組織変革、ウェルビーイングなどのテーマを手掛けている。
2児の母。好きな食べ物はドーナッツ。

「運悪く当たってしまうことがあり得る」「地域一帯の人々全てが等しく被害を受けるもの」かもしれません。
しかし、さまざまな被災地の取材を経験した私が皆さんにまずお知らせしたいのは、同じ災害に遭遇しても、それぞれの生活・人生に及ぼされる被害の影響というものは、決して、皆にとって同じ大きさではないのだということです。
残念ながら、災害前に立場の弱かった人ほど、より大変な目に遭う。それが災害の怖さのもう一つの側面です。
東日本大震災であった女性への性暴力
一例として、2011年3月の東日本大震災での、女性たちの被害の例をご紹介したいと思います。(「東日本大震災女性支援ネットワーク」の調査より、2013年)「夫が震災で死亡し、娘と避難する女性に避難所のリーダーが『大変だね。タオルや食べ物をあげるから夜、○○に来て』と性行為を強要した。女性は『もし嫌がったらここにいられなくなる。娘に被害が及ぶかもしれない』と応じざるを得なかった。」
「災害後に被災者の女性の元に元交際相手が車で駆けつけて関係を再開。女性は災害後に不安になり頼る人がほしかった。しかし、元交際相手は暴力や性暴力をふるった。」
※詳しくはハフポストの記事をご参照ください。
避難所で性行為を強要、DVが悪化…
…被災地であった女性への暴力その後
【東日本大震災】
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_60416a92c5b613cec15c66a2
例えば、避難所を運営するのは地域の自治会などです。平時の自治会を運営しているのは地域に長く住んでいる有力者で、リーダーとなるのも男性が圧倒的に多いのです。そのため、災害時にも避難所を取り仕切るのは、ほとんどが男性のリーダーとなります。
備蓄された支援物資をどう分配するか、スペースの割り振りをどうするか、運営に関わる仕事は誰が担当するのか、それらの取り仕切りを任されるリーダーには自然と権力が集まります。
例えば、男性リーダーには、生理用品や下着、着替えスペースなど、女性にとって何が必要不可欠なのかといった理解が及ばない可能性もあります。そして、それが女性たちの暮らしを困難にしています。
さらに、子育てや介護などの責任を日頃から1人で背負っている女性たちは、避難所でも身動きが取れず、さらに弱い立場になります。
また、経済の観点では、被害を受けた地元企業が経営を立て直すために真っ先に行いがちなのが、非正規雇用者の契約解除です。そうして、非正規で働く女性たちが経済的基盤を失うことになります。
こうしたさまざまな事情から、災害後、女性たちは特に社会的・経済的に弱い立場に置かれやすくなります。
性暴力はその中でも最も極端な例です。しかし、女性の弱みや不安につけこみ、優位な立場にある男性が性暴力を行うということの背景には、被災後に広がる権力勾配の格差が影響しています。

▲地震の被害が大きかった石川県珠洲市で全壊した自宅を見つめる家族
能登半島地震でもいまだに同じ構図
この数年で、ジェンダー平等の観点から世の中の仕組みを再検証する動きが進んできました。災害に関しても、女性にとって必要な物品を備蓄することや、避難所の運営リーダーに女性を増やす取り組みも各地で行われてはいます。しかし、2024年能登半島地震の被災地でもまだ、着替えスペースが設置されなかった避難所があったこと、避難所での炊き出しを女性だけがさせられている場所があったことなどが報じられました。
内閣府は女性を困難にさらさないという観点からの避難所運営マニュアルも制作し、一文を自治体に周知しています。そのほか、各種関係者の努力で以前より確実に改善はされています。しかし、2024年になっても地域レベルではまだこれらの知識が行き渡らず、さまざまな問題が積み残されたままになっていることが明らかになりました。
最初にわかりやすい例として、男女の格差についてお伝えしました。しかし、LGBTQを始めとする性的マイノリティの方々に関してももちろんそれぞれの困難があることを念頭におく必要があります。
弱い人のための特別な支援
そして、ジェンダーだけではありません。避難所生活が解消され、仮設住宅に入居する段階になると、元々あった別の格差が明るみに出ます。例えば、過疎地域などで広範な地域が被災した場合は、経済的・社会的基盤や自由がありすぐに動ける人、もしくは頼れる相手がいる人から被災地を離れて都会に出ていき、弱い立場の人ほどその場に留まる確率が高くなります。災害が起きやすい地域により弱い人が住むことにもなり、地域の経済や教育環境などもより疲弊していく……。
災害報道では、特定地域の差別に繋がりかねないという懸念からこうしたことは指摘しづらい部分があり「同じ被災者」という構図にせざるを得ません。しかし、私が取材した被災地では、多かれ少なかれ、復旧・復興の過程で、どこでもこうした構図が見られました。

▲珠洲市内の避難所。自主避難所を含めて44カ所に1,100人以上が避難している
女性、子ども、障がいのある人、持病のある人、経済的に弱い立場の人……。
だからこそ、災害前にその人が持っていた脆弱性の観点を抜きにして一律の支援をするだけでは、災害で格差が広がり、弱い人がより困難な状況に追い詰められていくことを止めることはできません。ダイバーシティ経営などの文脈で「イコーリティ(平等)ではなく、エクイティ(公平)」を目指すべきだというお話を耳にされたことがあるかもしれません。支援の内容そのものを平等にするのではなく、人に合わせたサポートを用意することによって、全体のパフォーマンスが向上するという意味です。
それと同じく、災害支援においても、平等ではなく、公平をめざすことでしか、地域一体の復旧・復興は成し遂げられません。支援においても、より弱い人に合わせた支援を考えるという視点が欠かせないと思います。
そして、その視点を災害時に急に芽生えさせることは絶対に不可能です。平時から格差を減らすための取り組みをすること、どんな取り組みが必要かを、それぞれの立場で決めておくことが大切です。
リアルな体験を企業に持ち帰る
さて、ここからは「災害に対して企業ができること」をお話したいと思います。最近、メディア事業者として、社内のファイナンス部門と事業継続計画(BCP)の策定作業を進める中で、ふと感じたことがあります。それは、さまざまな企業の中でこれらの計画を作っている方々の中に、「実際の災害現場を体験している人がどれぐらいいるのだろうか?」ということです。
被災したことがある人、新聞社やテレビ局など、ニュースの取材に関わった人ならば多かれ少なかれ、「災害とはこういうものだ」というイメージがあると思います。しかしそれ以外の皆さんはどうだろうか……と。
もし、企業の中にその視点を獲得することが必要だと感じるようでしたら、企業として社員を災害ボランティアなどとして派遣するなどのプログラムを実践してみるというのはいかがでしょうか? 有志などから小さく始めることも有効でしょう。
社会貢献と同時に、災害時に企業が社会にとっての力を発揮するため、事業を継続するためにも、さまざまな面で必ずその経験は生きてくることになるでしょう。
気候変動と災害、企業の役割
さて、災害を考えるうえで、最後にもう一つ、現代において気候変動による災害の激甚化という視点は欠かせないものです。2024年9月、年始に起きた地震から少しずつ復興が進んでいた石川県・能登半島を記録的な豪雨が襲いました。現地では20以上の川が氾濫し、15人が亡くなりました。
気象庁などは12月9日、この大雨について地球温暖化の影響を評価したところ、総雨量(9時間積算雨量)が15%増加していたと結論付けました。
つまり、気候変動がこの豪雨をより激しいものにし、人々の生命を奪ったということが、既に日本でも明確になっているのです。

▲埋もれた車を出すため、積み上がったガレキを取り除く消防隊員
2025年1月に起きたアメリカ・カリフォルニア州の大規模な山火事も、同じように気候変動の影響が指摘されています。現地では2024年5月以降にほとんどまともな雨が降っておらず、非常に乾燥した危険な状態だったことが明らかになっています。
気候変動・地球温暖化は、人間が暮らしのために、大量の温室効果ガスを排出してきたために起こっていることがすでに科学的に明らかになっています。
そして、「産業革命前の水準からの平均気温上昇を1.5度に抑える」というパリ協定で世界各国が合意した目標を達成できなければ、今よりももっとひどい災害が頻発する世界になるということが明らかになっています。
これに対して、2024年末時点で各国が提出している温室効果ガスの排出量削減目標を全部達成したとしても、気温はこの先、2.6〜2.8度上昇してしまうということがわかっています。つまり、残念ながらまだ日本を含む各国の目標は「低すぎる」のです。
世界中の科学者が、最新の科学的知見をもとにまとめた気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次報告書の計算では、日本は2035年度に、2013年度比で少なくとも66%の排出量削減が必要だとされています。一方、この執筆時点(2025年1月)で検討中の日本の目標案は60%削減。実は気候変動を食い止められる水準ではないという状況です。
それに対して、気候変動に対して積極的に取り組もうとする動きが、企業の中にもあります。そのような企業の連合組織(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)は、政府案に対して目標の引き上げを要望しています。
もちろん気候変動対策を進めるためには、現状のビジネス環境を大きく変更する必要があるため、短期的には負担にもなり得るものでしょう。しかし、災害が頻発する世界になってしまっては、これまで通りのビジネスを維持することは不可能になります。
事業継続のためにも、新たな産業を生み出すためにも、野心的な目標の設定は決してマイナスばかりではありません。
気候変動が災害という形で深刻な影響をもたらしている現在においては、災害対策は、土木やインフラ、備蓄などだけにとどまりません。
より大きな規模での防災対策として、企業には、気候変動を食い止めるためにできること、という観点からも、その社会的責任を捉え直していく必要があると思います。

▲能登半島豪雨直後の現地の様子
2025.8 掲載